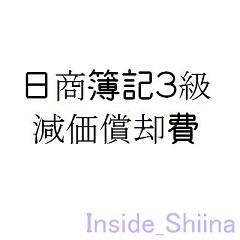
こんにちは。シーナと申します。
「日商簿記2級」の受験を目指している私が、復習のために「日商簿記3級」の勉強を始めた時に感じた疑問や勉強したことを纏めていくシリーズです。
今回は、第5問の「精算表」と「財務諸表」に高頻度で出題される「固定資産」における
「減価償却費」の定額法による仕訳についてです。
第1問の仕訳問題にもよく出題されます。
これから簿記を受験するあなたの参考になれば幸いです。
- はじめに
- 固定資産とは
- 減価償却とは
- 固定資産の仕訳とは
- 購入時の仕訳
- 決算時の仕訳
- 売却時の仕訳
- 第1問「仕訳問題」での減価償却費の計算方法、求め方
- 精算表での減価償却費の計算方法、求め方
- 財務諸表での減価償却費の計算方法、求め方
- 過去問のすすめ
- おすすめ過去問集の理由
- 出題範囲は再確認しましょう
- 仕訳が苦手なあなたに
- 終わりに
- 関連記事です。
はじめに
第5問の「精算表」について全体的な解き方、求め方を紹介している
以下の記事を先にご確認ください。
第1問の「仕訳問題」については、以下の記事で紹介しています。
固定資産とは
- 会社が保有する営業用などの「土地」
- 店舗や倉庫などの「建物」
- 机やパソコンなどの「備品」
- 社用車や配送用トラックなどの「車両」
これらのように会社が営業活動を行うために所有する資産を固定資産と呼びます。
減価償却とは
固定資産の内、「土地」以外は時間経過と共に日々価値が下がります。
そのため帳簿上の資産価値も購入時の価値より減少させる必要があります。
価値の減少を計算し、費用として計上する処理のことを減価償却と呼びます。
「償却」には「費用化」という意味があります。
固定資産の価値が減って費用化(償却)する=減価償却となります。
本来は毎日価値は下がっているのですが、毎日処理することは現実的ではないため、
基本的には決算時に処理します。この処理が第5問で出題されます。
ちなみに「土地」は(帳簿上の)価値が下がることはありません。
上がることもありません。
固定資産の仕訳とは
購入時、決算時、売却時についてそれぞれ説明します。
まずは基本的な考え方を確認してください。
スポンサーリンク
購入時の仕訳
以下の状況を想定します。
シーナ商店は、201X年1月1日に業務用デスクを49万円で購入し、送料1万円と共に月末に支払うことにした。
この場合、仕訳は以下になります。
備品500,000 |未払金500,000
ちなみにこの例では1月1日に購入していますが、現実では(試験でも)、
資産の購入や売却は期中に発生しますので、その場合は月割で減価償却費を計算します。
この辺の計算が減価償却費の試験におけるポイントになります。
これについては後述する具体的な解き方のときに説明します。
なお、固定資産は商品ではありませんので、「買掛金」ではなく「未払金」で処理します。
固定資産の勘定科目
業務用デスクは、資産の勘定科目である「備品」です。
「固定資産」という勘定科目はありません。
それぞれの物品に対応する勘定科目を使用します。
試験では使用する勘定科目は分かるように示されますので、あまり気にしなくて大丈夫です。
諸費用(付随費用)の扱い
商品や資産を購入する際に必要な送料や手数料などは、諸費用(付随費用)と言います。
この付随費用は取得原価に含めます。
業務用デスクを利用するためには手元に届けて貰わなくてはなりません。
業務用デスクを利用するために必要な費用ですので、取得原価に含めます。
取得原価=購入代金+付随費用となります。
これは商品の「仕入」でも同じです。
※少し話がそれますが、問題文に「先方負担」という記述がある場合は、
問題文の指示に従います。大体は、立替金 or 売掛金で処理されます。
※売掛金で処理する場合、付随費用分は売上には含まれませんので注意してください。
なお、「原価」と「減価」。
読みは一緒ですが、漢字の間違いには気を付けてください。
誤字・脱字は間違いになります。
間違えやすい誤字・脱字は以下の記事で紹介しています。
スポンサーリンク
決算時の仕訳
以下の状況を想定します。
201X年12月31日となった。
業務用デスクの耐用年数は3年、残存価額は取得原価の10%である。
この場合、仕訳は以下になります。
減価償却費150,000 |備品減価償却累計額150,000
※複数の資産を持っていても(普通持っていますが)、全て「減価償却費」の勘定科目を使用します。備品減価償却費とはしません。
その区別は「○○減価償却累計額」の勘定科目で行います。
ただし、「○○減価償却累計額」と資産名を記載するのは、内部用の資料だけです。
外部向けの財務諸表(貸借対照表)では「減価償却累計額」となります。
後ほど説明しますが、各資産の下に記載しますので、わざわざ書かなくても分かります。
この点もポイントになりますので、必ず覚えておいてください。
減価償却費の計算方法は3つある
減価償却費の計算方法には、以下の3つがあります。
- 定額法(ていがくほう)
- 定率法(ていりつほう)
- 生産高比例法(せいさんだかひれいほう)
日商簿記3級では、定額法のみが対象となります。
定率法、生産高比例法は、日商簿記2級から出題されます。
そのため当記事では、定額法についてご説明します。
定額法による減価償却費の計算式
決算において業務用デスクの資産価値が下がった分を費用として計上します。
今回は丸1年間使用しています。
定額法は、毎年定額分だけ固定資産の価値が下がると考えて、減価償却費の計算をします。
計算式は、以下のようになります。
減価償却費=(取得原価ー残存価額)/(耐用年数)
もう一度、決算時の状況を記載します。
201X年12月31日となった。
業務用デスクの耐用年数は3年、残存価額は取得原価の10%である。
取得原価は50万円ですので、その10%である残存価額(ざんぞんかがく)は5万円です。
1年間の減価償却費は、(50万円-5万円)/3年で、15万円となります。
電卓で計算する場合は、500,000×0.9÷3とすると簡単に計算できます。
毎年、15万円価値が下がり、4年目(購入から3年後)には残存価額の5万円が残ります。
5年目以降はこれ以上価値が下がりませんので特に考慮する必要はありません。

電卓の使い方については以下の記事で紹介しています。
残存価額(ざんぞんかがく)とは
耐用年数が経過した後(資産を使い終わった後)に残る価値のことです。
処分価額(スクラップ価額)とも言います。
要するに売却するときの価格です。
ただし、2007年の税制改革により現在は残存価額を0円にすることが認められたため、
残存価額が0円というケースでの出題も増えています。
(2007年以前は、残存価額を10%にしておく必要がありました。)
なお、残存価額が0円の場合、
本当に0円にしてしまうと帳簿上はその資産は存在しないことになります。
しかし現実ではその資産は存在して使用も出来るわけで、税務署に調査に入られると帳簿上に存在しない隠し資産と見做されかねません。
何も知らない人は、その資産が減価償却済みかどうかは分かりません。
そのため残存価額が「0円」になっても帳簿上は「1円」とする場合が現実では普通です。
その資産はちゃんと把握しています。減価償却が完了したものなのですと言えるわけです。
この「1円」のことを備忘価額(びぼうかがく)と言います。
精算表や財務諸表で1円と記載させる問題が今後増えてくる可能性があります。
日商簿記3級第148回の第5問で初めて出題されています。
なお、第148回の場合は、問題文で丁寧に説明されているため、1円と記載することを
知らなくとも(多少不安になるとは思いますが)問題はありませんでした。
ただ、おそらく「今後はこのような問題も出題するよ」という出題者側からの
メッセージだと考えられますから、今後は丁寧な説明がない可能性があります。
そういうものがあるということは覚えておいた方がよいと思います。
減価償却費は月割計算
今回のケースでは丸1年間利用していますが、当期中の7月23日に購入していた場合は、
決算時には6ヶ月しか利用していませんので、減価償却費は7万5千円になります。
減価償却費は月割計算となります。
12-7と計算すると間違えますので、7,8,9,10,11,12と指折り数えた方が確実です。
減価償却の処理方法は2つある
先ほど計算方法は3つあると説明しましたが、減価償却費を求めた後の処理方法には、
以下の2つがあります。
- 直接控除法
- 間接控除法
前述の決算時の仕訳は間接控除法になります。
減価償却費150,000 |備品減価償却累計額150,000
日商簿記3級では元々間接控除法がよく出題されていましたが、試験範囲の改定により、直接控除法は出題されることは無くなりました。
※日商簿記2級では直接控除法も出題されます。
試験範囲の改定については、後述しています。
当記事は簿記3級の実践編であるため、間接控除法についてのみ説明します。
特に断りが無い場合は、間接控除法を前提として全て仕訳しています。
間接控除法とは
言葉の通り、間接的に固定資産の価値を控除します(差し引く)。
「備品」から直接「減価償却費」を引くのではなく、資産のマイナス勘定である「○○減価償却累計額」という勘定科目を利用して、間接的に「減価償却費」を引きます。
つまり、関節控除法では、各固定資産は購入時の取得原価の価格のまま帳簿上に存在します。
残存価額を知りたい場合は、「○○減価償却累計額」を差し引く必要があります。
間接控除法のメリットは、購入時の取得原価が帳簿上で分かることです。
スポンサーリンク
売却時の仕訳
第1問の仕訳問題でもよく出題されます。
以下の状況を想定します。
購入からぴったり2年後の201X年1月1日に業務用デスクを売却した。
取得原価は50万円、減価償却累計額は30万円、売却額は25万円である。
代金は後で受け取る。
この場合、仕訳は以下になります。
※2行になっていますが、1つの仕訳です。
未収入金 250,000 |備品 500,000
備品減価償却累計額300,000 |固定資産売却益 50,000
売却時には損益が発生します。
「固定資産売却益」もしくは「固定資産売却損」の勘定科目で処理します。
「備品売却益」や「備品売却損」のように固定資産の名前を付ける場合もあります。
なお、固定資産は商品ではありませんので、「売掛金」ではなく「未収入金」で処理します。
上記の例で売却額が15万円である場合、仕訳は以下になります。
※3行になっていますが、1つの仕訳です。
未収入金 150,000 |備品 500,000
備品減価償却累計額300,000 |
固定資産売却損 50,000 |
期中での売却時の仕訳
減価償却費は月割計算です。
使用した期間分(月数分)の減価償却費を計算する必要があります。
以下の状況を想定します。
購入から2年3ヶ月後の201X年3月24日に業務用デスクを売却した。
取得原価は50万円、耐用年数は3年、残存価額は取得原価の10%、売却額は25万円である。
代金は後で受け取る。
この場合、仕訳は以下になります。
※3行になっていますが、1つの仕訳です。
未収入金 250,000 |備品 500,000
備品減価償却累計額300,000 |固定資産売却益 87,500
減価償却費 37,500 |
3ヶ月分の減価償却費は、(50万円-5万円)/3年に3/12で、37,500円となります。
「○○減価償却累計額」の勘定科目に加算するのは、決算時のみです。
期中の減価償却費は「減価償却費」の勘定科目で処理します。
ここがポイントです。
ここまでで基本的な考え方の説明は終了です。
それでは以降で実際の試験での求め方を紹介します。
第1問「仕訳問題」での減価償却費の計算方法、求め方
第149回の問題を例にとって説明します。
日商簿記3級第149回問題文より引用。
5.不要になった備品(取得原価¥700,000、減価償却累計額¥560,000、間接法で記帳)を期首に¥20,000で売却し、代金は月末に受け取ることとした。
出典:日商簿記3級平成30年度第149回簿記検定試験問題用紙
※使用する勘定科目は列挙されますので、その中から最も適当と思われるものを選びます。
仕訳は以下になります。
※3行になっていますが、1つの仕訳です。
未収入金 20,000 |備品 700,000
備品減価償却累計額560,000 |
固定資産売却損 120,000 |
※試験では勘定科目の順番は自由です。上記の順番でなくても構いません。
特に仕訳自体に解説は不要と思います。
備品の帳簿上の価値は14,000円(700,000-560,000)ですので、20,000円で売却すると
120,000円損したことになります。
ポイントは、勘定科目です。
「備品減価償却累計額」が正解です。
「減価償却累計額」と記述すると間違いです。
実際の試験中は意外と単純なミスをしてしまいます。
仕訳も5問目ぐらいになると慣れてきて、列挙されている勘定科目を確認せずに、
問題文にある「減価償却累計額」をそのまま記載してしまいます。
はい。私のことです。
財務諸表では「減価償却累計額」と記載しますので、違和感も覚えにくいです。
私は見直しで運よく見つけられましたが、仕訳は完璧だと考えていましたので、
時間がかなり余らなかったら第1問の仕訳問題は見直しもしなかったと思います。
勉強した人ほど、仕訳は自然と頭に出てくるため、単純なミスをしがちです。
間違っていないと自信があるときほど見直しをしましょう。
精算表での減価償却費の計算方法、求め方
第147回の問題を例にとって説明します。
日商簿記3級第147回問題文より引用。
6.建物および備品について定額法で減価償却を行う。
建物:残存価額ゼロ 耐用年数30年
備品:残存価額ゼロ 耐用年数4年
出典:日商簿記3級平成28年度第147回簿記検定試験問題用紙
答案用紙の精算表は以下のようになっています。
関係する部分だけ抜粋します。

残存価額がどちらもゼロですので、単純に残高試算表の金額を耐用年数で割ります。
建物:870,000÷30=29,000
備品:360,000÷4=90,000
減価償却費は資産ごとに分かれていませんので、合計します。
減価償却費=29,000+90,000=119,000
この計算結果を踏まえて、精算表は以下のようになります。

※修正記入欄(に限りませんが)は必ず貸借が一致します。
貸方(or借方)に合計119,000円記入すれば、必ず貸方(or借方)で合計119,000円が記入されます。
このルールを覚えておけば精算表は簡単になると思います。
間接法ですので、資産である「建物」、「備品」はそのまま貸借対照表欄に記載します。
当然ですが、この部分に配点はありません。
基本的には減価償却費に配点が付くと思います。
ごく稀に勘定科目欄に「減価償却費」が無く、受験者に記載させる場合があります。
「○○減価償却費」ではありませんので、ご注意ください。
財務諸表での減価償却費の計算方法、求め方
第149回の問題を例にとって説明します。
(1)決算整理前残高試算表
日商簿記3級第149回問題文より関係するところだけ抜粋しています。

(2)決算整理事項等
日商簿記3級第149回問題文より引用。
3.仮払金¥120,000は、その全額が9月1日に購入した備品に対する支払いであることが判明した。
6.備品について、残存価額をゼロ、耐用年数を8年とする定額法により減価償却を行う。当期新たに取得した備品についても同様の条件で減価償却費を月割により計算する。
出典:日商簿記3級平成30年度第149回簿記検定試験問題用紙
日商簿記3級第149回答案用紙より関係するところだけ抜粋しています。
灰色の部分に数字を入れます。

ポイントは既存の備品と問題文3で期中に購入した備品を分けて減価償却費を計算する
ということです。
また残存価額はゼロですので、耐用年数の8年で割るだけです。
既存の備品:2,000,000円 減価償却費:250,000円/年
新規の備品:120,000円 減価償却費:15,000円/年
そして新規の備品は9月1日に購入しましたので、決算である12月末まで、
9,10,11,12と4ヶ月間だけ使用しています。
12-9とすると間違えます。
指折り数えた方が確実です。
そのため決算時点で計上する費用は4ヶ月分(15,000×4÷12=)5,000円となります。
この計算結果を踏まえて、財務諸表は以下のようになります。

配点はやはり損益計算書の減価償却費の金額にのみある(貸借対照表の方にはない)という
予想が多いようです。
それで期中での売却時の仕訳(減価償却費)の考え方を理解しているかどうかが分かります
からね。
なお、貸借対照表の「減価償却累計額」が空欄で受験者に記載させることがあります。
繰り返しとなりますが、「○○減価償却累計額」ではありませんので、ご注意ください。
備品の下に記載するので、わざわざ記載しなくても分かるということです。
金額欄の「△」も記載する必要があります。マイナスという意味です。
忘れずに記載しましょう。
いかがでしょうか。
ポイントさえ押さえればそれほど難しくはないのではないでしょうか。
後はひたすら問題を解きましょう。
過去問のすすめ
慣れるためにも過去問題集は必ず解きましょう。
過去問を解くときは、第5問なら第5問だけを一気に解きます。
そうすると大体パターンが分かりますし、自分がミスするポイントも分かります。
ミスしたポイントは紙に書き出しておくと、自分がよく間違える箇所が分かります。
私は第3問や5問の過去問でよく「約束手形」と「小切手」の仕訳を間違えました。
つい「現金」ではなく「受取手形」に仕訳してしまうのです。
簡単と思った時(さらっと仕訳した時)ほど間違えています。
そのため繰り返しとなりますが、過去問を解いたときに間違えた理由、自分が勘違いしやすい仕訳は紙に書き出しておくことをお勧めします。
試験当日に試験会場へ向かうときに眺められます。
私は以下のようなものを作っておきました。
一部ですが。汚い字で申し訳ありません。
ブログ公開用に作り直す気力はありませんでした。

おすすめ過去問集の理由
過去問題集はたくさん出ていますが、私が実際に利用しておすすめする過去問題集は以下の記事で紹介しています。
おすすめする理由は、出題範囲から外れた部分(正確には配慮するです)が同レベルの出題範囲内の問題に改編されているからです。
単純に昔の出題範囲のままの(つまりこれから受験する回には出題されない)過去問を解くよりも効率的です。
詳細は以下の記事を見てください。
最新版はネット試験にも対応していますよ。
出題範囲は再確認しましょう
何事も相手を知らなければなりません。
2019年度(第152回試験)から簿記3級は試験範囲が改定されます。
その辺りの事情については、以下の記事で紹介しています。
思い切って、試験範囲から除外される部分は勉強しないという方法もあります。
現在の実務でも、なかなか行わないものが多いですから。
前述の過去問題集は、この辺が考慮されていますのでおすすめです。
仕訳が苦手なあなたに
どうしても仕訳が苦手という方、特に学生や社会人になったばかりの人は、商取引の(掛取引などの)イメージがしにくいと思います。
これは仕方がありません。
そのような時は以下の書籍がおすすめです。
前述の過去問題集を出版しているWeb型予備校「ネットスクール」の代表である
「桑原 知之」氏の著書
「脳科学×仕訳集 日商簿記3級 (合格するにはワケがある)」です。
仕訳集とありますが、仕訳だけではなく、簿記自体の考え方を学べます。
私の簿記の考え方はこの本に基づいています。
2021年3月に第3版が販売されています。
価格は2021年4月現在で1,320円(税込)です。
仕訳の仕組みから理解できますし、出題実績の高い順番に説明されていますので、効率よく簿記3級に必要な知識を学ぶことができます。
ちなみに掛取引とは後払いのことです。
波平がよく飲み屋の支払でしていたやつ(ツケといて!)と仕組みは同じです。
(最近テレビを見ていませんので、もうしていないかもしれませんが。)
企業間の取引は掛取引が基本です。信用商売ということですね。
終わりに
あなたの参考になれば幸いです。
それでは、また。
関連記事です。
「減価償却費」同様、第5問の精算表で高頻度で出題される「貸倒引当金」の解き方です。
同じく第5問の精算表で高頻度で出題される「売上原価」の解き方です。
日商簿記3級で使用する勘定科目の一覧を纏めました。
第1問の「仕訳問題」への対応方法、解き方のコツの紹介です。
第5問と同じ配点である第3問について具体的な解き方の紹介です。
試験全体について攻略法と問題毎の時間配分についても紹介しています。
試験までの段取りと前日、当日の過ごし方、タイムスケジュールも紹介しています。
間違えやすい誤字脱字を紹介しています。
