
こんにちは。シーナと申します。
「日商簿記2級」の受験を目指している私が、復習のために「日商簿記3級」の勉強を始めた時に感じた疑問や勉強したことを纏めていくシリーズです。
第2回目である今回は、第1問の「仕訳問題」についてです。
これから簿記を受験するあなたの参考になれば幸いです。
- 日商簿記3級第1問の特徴
- 問題文にある「勘定科目」を使うこと
- 第1問のための勉強法(解き方のコツ)
- 出題範囲を再確認しましょう
- 出題傾向の分析について
- 勘定科目でこんがらがったあなたへ
- 勉強中に自分用メモを作りましょう
- 誤字脱字にもお気を付けください
- 仕訳が苦手なあなたに
- 日商簿記3級は独学で取得できるのか?
- 終わりに
- 関連記事です。
日商簿記3級第1問の特徴
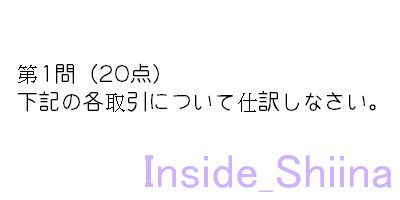
全5問の仕訳問題が出題されます。1問4点で計20点。これは毎回変わりません。
大体20分ぐらいで全て解答したいところです。
なお、第1問で使用する「勘定科目」は問題文に全て提示されています。
最も適当な勘定科目を選びます。
つまり、2番目に適当では間違いということです。
最初に勘定科目を一通りチェックする際に、分類ごとに分けておくとよいです。
大抵、資産、負債、費用、収益ごとに勘定科目が並んでいますので、線を引いて区切っておくと、後で確認しやすくなります。
問題文にある「勘定科目」を使うこと
必ず問題文の中にある「勘定科目」を使いましょう。
当たり前だと思われると思いますが、しっかり勉強した人ほど注意が必要です。
問題文(の取引)を読むと自然と仕訳ができるようになっていると思います。
そうすると問題を解き進めるほど、提示されている「勘定科目」をしっかり確認せずに
解答してしまいます。
はい。私のことです。
本番の試験は意外と緊張していますので、そんなことはしないよということをしてしまうものです。
※実際に商工会議所の講評でも問題文にない勘定科目を記載して間違える人が多数いるとされています。
私は合格は間違いないだろうと思いつつ時間が余ったため、第1問からしっかり見直しました。
そのおかげで運良く間違いに気付きましたので無事に修正できました。
間違っていないと思うと人は見直したりしません。
自信があるときほど、一旦解き終ったら、問題文にある「勘定科目」を
一字一句間違いなく使用しているか確認することをお勧めします。
ちなみに私は本来「備品減価償却累計額」のところを「減価償却累計額」としていました。
当然、そのままでは間違いになります。
第5問に出題される「損益計算書」では、「減価償却累計額」と記載するため勘違いしやすいところです。
「損益計算書」は第3者(外部)に公開するため、勘定科目の表記も変わります。
この辺は第5問の実践編でお伝えします。
本記事の下にある関連記事で第5問実践編へのリンクがあります。
第1問のための勉強法(解き方のコツ)
ポイントは、2つです。
1つ目:勉強方法・暗記について
最初から「勘定科目」を丸暗記するようなことは絶対にしないことです。
日商簿記3級は、商品売買に関するものがメインです。
そのため仕訳は商取引(の仕組み)をイメージ(理解するように)しながら、簿記の勉強を
進めていけば自然とできるようになります。
というより、そうしていかないとこの先で苦しむと思います。
日商簿記3級の合格だけが目的なら丸暗記でもよいです。
日商簿記2級以上を目標とする人や実務で簿記(の知識を含め)を使う人は、少し時間が掛かるかもしれませんが、暗記はやめて取引をイメージして学びましょう。
厳しい言い方になりますが、簿記に限らず丸暗記した知識なんて実務では応用も効きませんから役に立ちません。
そのため第1問に対する特別な勉強は必要ありません。
簿記の勉強をきちんと進めれば自然と解けるようになっています。
2つ目:問題文の解き方のコツについて
問題文を細かく区切ることです。
一度にすべて読み、全て纏めて考えるので、ややこしくなります。
センテンス毎にシャーペンで線を引いて、それぞれで仕訳してしまいしょう。
実際に出題された問題を基にご説明します。
日商簿記3級第149回の問題文より引用。
1.新田商店に¥600,000を貸し付け、同額の約束手形を受け取り、利息¥6,000を差し引いた残額を当店の普通預金口座から新田商店の普通預金口座に振り込んだ。
出典:日商簿記3級平成30年度第149回簿記検定試験問題用紙
この場合は、2つの文章に分けて、それぞれ仕訳します。
まず、以下の文章の仕訳を考えます。
新田商店に¥600,000を貸し付け、同額の約束手形を受け取り、
手形を使用して貸し付けていますので、仕訳はまず以下になります。
手形貸付金600,000 |
次に、以下の文章の仕訳を考えます。
利息¥6,000を差し引いた残額を当店の普通預金口座から新田商店の普通預金口座に振り込んだ。
利息6,000円は貸し付ける前に受け取り、差額を普通預金口座から振り込むようですので、
仕訳は以下になります。
|受取利息6,000
|普通預金594,000
後は、2つの仕訳を纏めるだけです。
※2行になっていますが、1つの仕訳です。
手形貸付金600,000 |受取利息6,000
|普通預金594,000
※貸方の受取利息と普通預金の順番は逆でも問題ありません。
もう一つ問題を見てみましょう。
日商簿記3級第149回の問題文より引用。
2.青森商店に商品¥480,000を売り上げ、代金は掛けとした。なお、商品の発送費(青森商店負担)¥10,000を現金で支払ったので、この分は掛代金に含めることとした。
出典:日商簿記3級平成30年度第149回簿記検定試験問題用紙
この場合は、元々2つの文章に分かれていますね。
それぞれ仕訳します。
まず、以下の文章の仕訳を考えます。
青森商店に商品¥480,000を売り上げ、代金は掛けとした。
仕訳は以下になります。
売掛金480,000 |売上480,000
次に、以下の文章の仕訳を考えます。
商品の発送費(青森商店負担)¥10,000を現金で支払ったので、この分は掛代金に含めることとした。
付随費用は先方負担ということです。問題文に指示がありますので、売掛金に含めます。
仕訳は以下になります。
売掛金10,000 |現金10,000
後は、2つの仕訳を纏めるだけです。
※2行になっていますが、1つの仕訳です。
売掛金490,000 |売上480,000
|現金10,000
※貸方の売上と現金の順番は逆でも問題ありません。
いかがでしょうか。
ちょっとしたことですが、分かりやすいのが一番です。
問題文には積極的に書き込みをしましょう。
出題範囲を再確認しましょう
何事も相手を知らなければなりません。
平成31年度(第152回試験)から簿記3級は試験範囲が改定されます。
そのため平成30年度の残りの試験(150回、151回)はチャンスとなっています。
思い切って、試験範囲から除外される部分は勉強しないという方法もあります。
2018年現在の実務でも、なかなか行わないものが多いですから。
実際、私が受けた第149回や前回の第150回では該当箇所は出題されませんでした。
現在は、新範囲に移行しています。
完全に新範囲に移行した第153回試験については、以下の記事で紹介しています。
出題傾向の分析について
過去問の出題傾向から、次の試験ではこの仕訳が出るというような推測は
しないほうがよいです。
仕事にしているプロでも間違えるのですから、リスクが高すぎます。
つまり、プロの推測についてもあまり当てにしないほうがよいです。
大体数パターン作って来ますので、どれかの何問かは当たりますよ。
逆にこれは出ないというものは信じてよいと思います。
運営元である商工会議所がそう言っている(正確には配慮するですが)わけですから。
勘定科目でこんがらがったあなたへ

勉強を進めると必ず一度は勘定科目でこんがらがります。
大丈夫です。必ず誰もが一度は通る道です。順調な証拠ですよ。
出来るだけ早くこんがらがりましょう。試験直前にそうなってしまうとつらいです。
「前受○○」、「前払○○」、「未払○○」、「未収○○」など、資産なのか負債なのか、
はたまた費用なのか分からなくなると思います。
また、簿記3級でこんがらがる大きな理由の1つに、個人事業主がメインという点があります。
個人事業主では会社と個人が不可分ですので、ぱっとイメージしにくいです。
帳簿はあくまで会社の立場で記帳(仕訳)します。
個人の感覚で考えると間違いやすくなります。
たとえば、「給料」。
個人では収益のような気がしますが、会社としては費用です。
人件費(の一部)です。
たとえば、貰って嬉しい「商品券」。
個人では資産のような気がしますが、発行(販売)する会社としては負債です。
後で商品と引き換えなければならない債務(義務)です。
資産なのは他店が発行した「他店商品券」です。
勉強中に自分用メモを作りましょう
暗記していると軌道修正にかなり苦労しますが、仕組みで覚えていれば。
落ち着いて考えれば分かります。
しかし、本番の試験では気が急いていますので、ついつい勘違いが発生しやすいです。
私は第3問や5問の過去問を解いたときによく「約束手形」と「小切手」の仕訳を間違えました。つい「現金」ではなく「受取手形」に仕訳してしまうのです。
簡単と思った時(さらっと仕訳した時)ほど間違えています。
そのため過去問を解いたときに間違えた理由、自分が勘違いしやすい仕訳は紙に書き出しておくことをお勧めします。
私は以下のようなものを作っておきました。
一部ですが。汚い字で申し訳ありません。公開用に作り直す気力はありませんでした。

また、試験直前には勘定科目も書き出しました。
試験当日の移動中に眺められるようにするためです。
暗記はしないこととお伝えしましたが、試験直前は暗記も必要です。
貸借対照表の勘定科目一覧。

損益計算書の勘定科目一覧。

以下に日商簿記3級で使用する勘定科目の一覧を纏めました。
仕訳の覚え方についても説明しています。
参考にどうぞ。
誤字脱字にもお気を付けください
簿記試験でも誤字脱字は間違いになります。
その辺の注意事項は間違えやすい誤字等と共に以下の記事で紹介しています。
仕訳が苦手なあなたに
どうしても仕訳が苦手という方、特に学生や社会人になったばかりの人は、商取引の(掛取引などの)イメージがしにくいと思います。
これは仕方がありません。
そのような時は以下の書籍がおすすめです。
前述の過去問題集を出版しているWeb型予備校「ネットスクール」の代表である
「桑原 知之」氏の著書
「脳科学×仕訳集 日商簿記3級 (合格するにはワケがある)」です。
仕訳集とありますが、仕訳だけではなく、簿記自体の考え方を学べます。
私の簿記の考え方はこの本に基づいています。
2021年3月に第3版が販売されています。
価格は2021年4月現在で1,320円(税込)です。
仕訳の仕組みから理解できますし、出題実績の高い順番に説明されていますので、効率よく簿記3級に必要な知識を学ぶことができます。
ちなみに掛取引とは後払いのことです。
波平がよく飲み屋の支払でしていたやつ(ツケといて!)と仕組みは同じです。
(最近テレビを見ていませんので、もうしていないかもしれませんが。)
企業間の取引は掛取引が基本です。信用商売ということですね。
日商簿記3級は独学で取得できるのか?
もしもあなたが独学にするか、通信講座を利用するか迷っている場合は、以下の記事を見てみてください。
勉強方法や試験範囲の改定など役立つ情報も一緒に紹介しています。
終わりに
今年度中の日商簿記2級の受験は無理だろうなと、そんな気がする今日この頃です。
ブログの更新が楽しくって、ということにしています。
他の時間を削ればよいだけなのですけどね。
自己研鑽とはそういうものですよね。
それでは、また。
関連記事です。
配点が大きい第3問「試算表」の解き方を紹介しています。
第3問と同じく配点が大きい5問「精算表」の解き方を紹介しています。
第2問もしくは第4問で出題される可能性のある伝票会計についてです。
高頻度で出題される問題に対する具体的な解き方対策です。
「貸倒引当金」問題についてです。
「売上原価」問題についてです。
「減価償却費」問題についてです。
簿記3級攻略の足掛かりとなる基本情報を纏めています。
簿記試験で必須になる電卓。選んで間違いのない電卓の紹介です。
貸借一致の計算時に使えるテクニックも紹介しています。
試験までの段取りと前日や当日の過ごし方、タイムスケジュールも紹介しています。
